映画公開記念春彼岸特集
映画 禅 ZEN の魅力
曹洞宗開祖・道元禅師の教え
それは現代人の道しるべ
2009年1月10日から全国ロードショーをしている映画『禅
ZEN』。曹洞宗の開祖である道元禅師を主人公にしたこの映画は、まさに現代人が生きていくエッセンスが詰まった作品であるといえる。人間の内面描写はもちろんのこと、色彩鮮やかな映像は、まるで絵画のようだ。
そこで第16回読売演劇大賞の杉村春子賞を受賞し、今回は映画『禅
ZEN』の主人公道元禅師を演じた中村勘太郎氏、監督・脚本をなさった高橋伴明氏のお二人に対談インタビューをさせて頂いた。歌舞伎と仏教、演じるということ、しつけや教育といったテーマといった内容から、思わず笑ってしまう映画の裏話にいたるまで、本音で語って下さった。
 歌舞伎俳優
歌舞伎俳優
中村勘太郎(なかむらかんたろう)
◆1981年、東京都出身。
86年に「盛綱陣屋」で初御目見得。翌年「門出二人桃太郎」の桃太郎役で二代目中村勘太郎を名乗り初舞台を踏む。歌舞伎以外にも、舞台、TV、映画など幅広く精力的な活動を続けており、これまでの主な仕事として「世界遺産」(TBS)のナレーション、「新選組!」(NHK)、映画『ターン』などがある。『禅
ZEN』は映画初主演作。
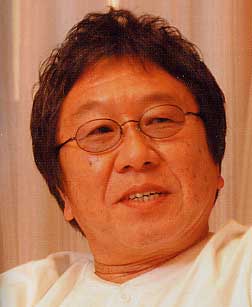 映画監督
映画監督
高橋判明(たかはしばんめい)
◆1949年、奈良市生まれ。
1972年「婦女暴行脱走犯」で監督デビュー。1982年に「TATTOO(刺青)あり」を監督、ヨコハマ映画祭監督賞を受賞。以後、監督・脚本・演出・プロデュースと幅広く活躍中。
代表作に「獅子王たちの夏」「迅雷―組長の身代金―」などがある。
中村勘太郎氏からみた道元禅師と仏教
【まさとみ☆】映画『禅 ZEN』を拝見し、勘太郎さんの所作は本当に美しく、その中にも力強さがあり、気品があってすごいと思いました。道元禅師を演じるにあたり、何か役作りをなされたのですか?
【勘太郎】歌舞伎は伝統芸能ということで、初役の場合は教わったことをそのまま演じます。映画などお芝居の時、役作りはしません。ですが、土台作りはしっかり考えます。現場に行ったら、その土台の上にどんな自由なものでも建てられるように。
今回の映画『禅 ZEN』では、演じた道元禅師の本を読んだり、永平寺に行ったりして、土台作りをしました。その上で、監督と話したり、現場でコミュニケーションを取ったりして作っていきました。ただ、道元禅師の本を読めば読むほど、この人の大きさや存在の大きさを感じて分からなくなってしまいました。歌舞伎俳優なので、歴史上の人物を演じるというのは、しばしばあるのですが。
【まさとみ☆】永平寺での体験というのは、ご自身いかがでしたか?
【勘太郎】僕の気質として、やってみなければ分からない、体験してみなければわからないということがあります。だから、永平寺での体験はとても大きなものでした。
特に、雲水さんたちの姿を見ましたね。坐禅を組むまでの一連の動きやしぐさ。永平寺は道元禅師がおつくりになって、道元禅師の教えが脈々と続いているわけじゃないですか。
歌舞伎も、初演からあったものを脈々と繋いでいます。仏教と歌舞伎はすごく似ています。坐禅するにおいても、理由や理屈は抜きで坐らせるんですって。そして、坐る形を徹底的にやらせる。歩いている時の左側通行や音を立てない所作など、形をまず徹底的に。それは歌舞伎も一緒なのです。
やはり、芝居でも坐禅でも、心が形になっているので、まず形を究める。心と形の両面をしっかりと究めるのは何十年も先です。心情過多になってはいけないですし、形だけになってしまってもいけない。心と形のバランスが大切だというのは、歌舞伎も坐禅も同じです。
【まさとみ☆】まず、形を徹底的に鍛えられるのですね。
【勘太郎】歌舞伎の稽古で、正座をさせられ続けたら足は痛いです。でも、痛ければ痛いほど、良い形になるのです。歌舞伎は答えを探す旅、かな。終りがないのです。年齢と共に身長や体型も違ってきますしね。
オンとオフの切り替え
【まさとみ☆】歌舞伎は何歳から始められたのですか?【勘太郎】踊りの稽古は2歳からです。
【まさとみ☆】歌舞伎はものすごい運動量で動きも激しいですよね。
【勘太郎】激しいものもありますし、ひたすら一時間半座りっぱなしというものもあります。
【まさとみ☆】すごい精神力と集中力を求められると思います。地方公演の時など、環境が変わると気持ちの面でも全く違うのでは?
【勘太郎】歌舞伎の公演中は、休演日がないのです。だいたい朝11時から夜9時までというスケジュールが一カ月弱続くので。その中で、だいたい4つか5つの役を演じています。
【まさとみ☆】精神力が強くないと、一カ月弱モチベーションをキープし続けるのは本当に難しいですね。
【勘太郎】やっぱり、精神力は必要とされますね。かといって、いつも緊張していては疲れてしまうので、緩める時は緩めていますよ。
【まさとみ☆】気持ちを緩めるときというのは、どういうことをなさっていらっしゃるのですか?
【勘太郎】舞台の中で、役によって緩急をつけています。たとえば、コメディーの時は緊張の糸を緩めてとか。そうしないと、25日間もたないのです。だから、どこに一番集中するものを持っていけば良いのか、自分でしっかりと組み立てないといけませんね。
【まさとみ☆】一日を上手に組み立てて、疲れはその日にリセットして翌日またスタート、ですね。
【勘太郎】なかなか疲れが取れないんですよ。後半になればなるほど、疲れてきちゃうので。
【まさとみ☆】自宅の中でオンオフというのは、どのように切り替えてらっしゃるのですか? 歌舞伎だけでなく、多方面で活躍なされている勘太郎さんですから、やはり、切り替えを上手になさっているのかと。
【勘太郎】本を読むのが好きですね。何か小物を集めたり、アロマにはまってみたり、サーフィンをやってみたり。
心とカラダのバランス
【まさとみ☆】一番調子が良い時、自分の中で完成度が高い時というのはどんな状態ですか?
【勘太郎】心がないと全く駄目ですね。でも、心が先行してしまう時は、全く自分が見えていません。 調子が良い時というのは、常にもうひとりの自分が、テンションの上がっている自分を見ていたります。そういう時は、僕は心と形のバランスが本当にうまくいっていると感じる時です。いつもそういう状態を目指しています。ただ、疲れていると俯瞰で見れなくなりがちですね。
歌舞伎は先祖からのリレーバトン
【まさとみ☆】歌舞伎のお芝居は日本古来の文化を伝え、それを観客が楽しむことができるもの。だからこそ、心と形を学び伝えるので、本当に厳しい稽古になっていくのだと思います。しつけや礼儀作法においても大変厳しかったのでは?
【勘太郎】厳しいというか、普通なんじゃないかな。挨拶はうるさく教わりましたね。今でも毎日、必ず家族全員で父親のお見送りをしています。そして、ガレージに車の音が聞こえたら、玄関までお出迎えをしていますね。お風呂も父親が一番風呂です。
【まさとみ☆】お友達に驚かれたことは何かありましたか?
【勘太郎】「自分の親になんで敬語なの?」と言われました。何故かは分からないですが、それは自然と染みついていますね。
伝承は伝言ゲーム+オリジナル
【勘太郎】歌舞伎の役者さんで88歳の人がいますが、今も舞台に出ていますからね。素晴らしいですよ。
【まさとみ☆】歌舞伎はまさにアンチエイジングの世界ですね! 勘太郎さんは何か運動をなさってらっしゃるのですか?
【勘太郎】歌舞伎だけで何もしていません。踊っていると、足がパンパンになります。洋服のサイズがないのです。太ももが太すぎてジーパンが入らなくて困りますね(笑)。
【まさとみ☆】歌舞伎の動きは、鏡などを見ながら自分でチェックするのですか?
【勘太郎】いいえ、見てもらいます。先輩に見ていただくのが一番ですね。
【まさとみ☆】歌舞伎はまさに人から人へとつないでいく文化。でも、誰かに何かを教えることだけでも難しいと思います。曹洞宗でも、道元禅師の教えを、お弟子さんが文書化したり、伝承したりしたことで今の世に残ってきました。伝えるということに関して、勘太郎さんはどのようにお考えですか?
【勘太郎】歌舞伎の世界は伝言ゲームですから。もちろん、僕は教わったものを教えるけれど、それがすべてだとは思っていません。広い目を持ってやってほしいなというのはあります。
【まさとみ☆】伝統を守っていく部分はそのままに、その中でご自身らしいものを出していく。
【勘太郎】そうですね。もちろん、最初に教わった時には、きっちりやらないといけません。その役を2度目に演じる時は自分らしさを出していくべきだし、僕自身も自分らしさが出るように努めています。
【まさとみ☆】ファンの方も、勘太郎さんらしさを観ることが嬉しいですものね。実際、勘太郎さんの自分らしさというのは、言葉で表現するとどんなものだと思いますか?
【勘太郎】僕は、自分でも自分がよく分からない人。つかみどころがないのです。だから、言葉で表現するのは難しいですね。自分で自分がよく分からないから、仏門に入るのが一番良いのかな(笑)。
【まさとみ☆】仏門の世界を演じられて、どう思いましたか?
【勘太郎】厳しい世界ということをすごく思いました。
【まさとみ☆】歌舞伎の世界もすごく大変じゃないですか?
【勘太郎】いやいや。歌舞伎というか役者なんて正反対の欲まみれですから。だって、そうですよ。人を楽しませようと思っても、自分が良いと思われたいし、どうしたら綺麗に見せることができるのかとか、たえず自分に目を向けています。自分が楽しくないと、観ている方へ楽しさが伝わりませんからね。
【まさとみ☆】僧侶の方の生活はものすごく禁欲的ですよね。だからこそ、永平寺の修行僧の方はとても透明感がありますね。【勘太郎】すごいですね。3、4か月くらい修行をしているとでビタミン不足で脚気になるっていいますからね。雲水さんでメガネをかけている方が多いでしょう。そこまでしているから凄いですよ。
【まさとみ☆】まさに、命をかけてということですものね。
【勘太郎】自分のためではなく、人のためにじゃないですか。役者なんて、自分の快楽のためにですから、言ってみれば(笑)。
【まさとみ☆】やっぱり、人は自分が楽しくないと(笑)。
【勘太郎】僕たちはいろいろな人に見てもらい、喜んでもらったり褒めてもらうことが楽しいですから。
【まさとみ☆】永平寺での体験で、何が勘太郎さんにとってきつかったですか?
【勘太郎】お肉を食べられなかったことです。
【まさとみ☆】それでは、食事の量が足りなかったのでは?
【勘太郎】それで痩せるかと思ったのですが、逆に太りました(笑)。動かないでしょう。本当に朝から座りっぱなしなのです。
【まさとみ☆】歌舞伎は本当に激しい動きをなさってらっしゃるのですね。衣装も相当の重量がありそうですね。
【勘太郎】昔の生地と縫製なので、本当に重いです。でもやっぱり、それが舞台上では綺麗なんですよ。
道元禅師を演じてからの変化
【まさとみ☆】道元禅師を演じたことで、自分の生活の中で何か変化はありますか?
【勘太郎】今まで、飛んだり跳ねたり、ハツラツとした役が多かったのです。今回の道元禅師役では、心の中の穏やかさだとか、内面を見つめ、自分自身と向き合い観察することを大切にしました。役柄ではテンパっている自分を演じているけれど、実際にはそれを俯瞰で見ている自分がいる。
【まさとみ☆】それは本当に心が穏やかでないと見ることができないですよね。日常生活では何か変わられたことはありますか?
【勘太郎】あまり怒ることがなくなりましたね。
【まさとみ☆】実際にお会いして、とても穏やかな印象を受けるのですが、荒々しい性分なのですか?
【勘太郎】いやいや、僕は気難しいですし、短気です(笑)。
【まさとみ☆】もうひとりの自分が、常に抑えてらっしゃるということですね。自分を見つめることは、本当に難しいことですね。
【勘太郎】ありのままというのは本当に難しいですね。やっぱりどうしても自分をよく見せようとしたり、人から良く思われたいと思います。道元禅師のように、ありのままであることはとても格好良いことだと思います。 それから、永平寺で座布団を買ってきて、うちで坐っています。坐れる時は45分くらい坐りますね。一籌ですか、お線香1本分。【まさとみ☆】撮影中のエピソードで何かございますか?
【勘太郎】お弁当が出た時にお肉とお魚のどちらかを選ぶのですが、坊主の格好をしているからか、どうしても魚のほうを選んでしまいましたね(笑)。
中村家のしつけ
【まさとみ☆】日本古来からの風習や行事に関して、勘太郎さんの家ではどのようになさっているのですか?
【勘太郎】お彼岸やお盆はもちろん、送り火もお迎えもやります。お墓参りは、命日はもちろん月命日にも必ず行きます。今の僕があるのは、本当に先祖のおかげですから。
【まさとみ☆】小さい頃から教わってきたのですか?
【勘太郎】そうですね。しつけに関しては、ほとんど毎日。だから、体に染みついてますね。母親には、言うことを聞かないと平手で叩かれました。しかも、指輪の石のほうを手の平に向けるんです(笑)。叩かれて階段から落ちたこともありました。
【まさとみ☆】それは強いお母様ですね。しつけはカラダで覚えないと身に付かないものでもありますよね。今、学校の先生に叩かれたと訴える親のことが報道されていますが。何か違和感を感じますね。【勘太郎】あれはおかしいですよね。だって、僕の世代でも先生によく叩かれましたよ。言ったって分からないのだから、体に覚えさせないと。
【まさとみ☆】お母様は叱るときは思いっきり叱る反面、褒める時は思いっきり褒めて下さったのですか?
【勘太郎】全然。それは舞台の稽古の時でも同じです。できないのは自分の稽古不足ですから。それは怒られます。だって、できるのにそのレベルまで至っていない。
【まさとみ☆】教えたことは次の日までにできていないといけない。
【勘太郎】それは最低限。教えた瞬間にできていないと駄目です。同じことで2回怒らせると、もう教えてくれない。
【まさとみ☆】目で見て、口で言える。体で覚えなくては駄目なのですね。ある意味、僧侶よりも歌舞伎の世界のほうが厳しいですね。
【勘太郎】そうですね。挨拶に関しては、父も厳しかったです。うちの父は学校の勉強のことなどは一切口を出さなかったのですが、挨拶に関しては本当に厳しかったです。ご飯を食べる時のマナーなどの所作に関しても、厳しく注意されました。 だからなのか、仏教は結構好きな世界です。ストイックで自分を追い込む道元禅師は、どこか自分の中にも共通するものがあるような気がして惹きつけられます。
歌舞伎は子供の頃からやっていますが、生半可な気持ちではできませんし、ほかの人たちに失礼です。僕は自分の意志で歌舞伎の道に入りました。中学を卒業する時に、ダイニングに弟と呼ばれまして。父親から歌舞伎をやるのかやらないのかを問われ、自分で選択させてもらいました。そのことは本当に感謝しています。
【まさとみ☆】勘太郎さんは、一枚づつタマネギの皮をはがすように、自分自身を深く探求しているからこそ「つかみどころのない人間」だとご自身を分析なさるのですね。それって、自分と向き合っているからこそですし、本当に日々精神の修行を積んでらっしゃるのだと感じました。勘太郎さんにとって、今回主演なさった映画『禅ZEN』はどういった映画だと言えますか?
【勘太郎】どこで爆発して何かというものでもない。本当に静かな湖面のような、穏やかな映画です。
【まさとみ☆】私は試写会で拝見しましたが、今の自分と、10年後の自分が観る感想は全く変わっている。そんな映画だなと思いました。
【勘太郎】そうです。絶対違うと思います。僕も道元禅師を演じさせていただきましたが、今の自分と、30歳、40歳と年を重ねるごとに、見えてくるものが違うと思いますね。 3月には2年ぶりにお休みを頂けるので、永平寺さんへお礼のごあいさつへ行こうと思っています。【まさとみ☆】今日はどうもありがとうございました。
高橋からみた道元禅師と仏教
【まさとみ☆】道元禅師は本当にストイックな方ですね。彼の生き方は、欲まみれの俗世間とは一切かけ離れていて、無駄がないですね。
【高橋】確かに無駄がない。映画『禅』を通して、近代合理主義を批判したかったのです。道元さんの絶対合理主義はすごい。その合理精神は、日常生活に必ずいかせるはずです。 例えば僕は、風呂の入り方というのは決まっている。それが一番無駄なくという気分ですね。
【まさとみ☆】高橋監督は、常に日常生活をつつがなく合理的に過ごされるのですね。
【高橋】そうありたいと思いますけど。やっぱり我々の仕事って、無駄なことが大事だったりします。ある一面だけはすごくこだわり、それ以外のところでは、人以上に余計なことをしていると思います。俯瞰で見たり、地べたからも見ないといけない。僕は人間観察が趣味で、電車に乗ると誰かターゲットを決めてずっと見ています。人間ってなかなか面白いことをするんです。こういうのが仕事で生かされることって多いですよ。「こんなこと、人ってついしてしまうことがあるだろう」なんて話を役者にすると、結構納得してくれますよ。
【まさとみ☆】それがきっと、人間の生々しさや演技になるのですね。
【高橋】そういうものを持っていないと、演技者側が演技者の引き出しで、僕にないものを出してきた時に、それを受け入れられない。俺もいっぱい持っているし、相手も持っている。俺が持っていないものを出してくれたら、「おお、そうきたか」と感動しちゃうのです。「こうしてくれ」というのはないです。自分がイメージしていたことと違うことをしてくれるほうが、得した気分になれる。
高橋監督と仏教との関係
【まさとみ☆】仏教は日常生活とはかけ離れた、自分に厳しくストイックな世界という印象ですが、映画『禅』では、厳しいだけでなく、静かな広がりのようなものが伝わってきました。
【高橋】僕もちょっと仏教をかじっているのです。ここ25、26年。普通の生活をしながら、在家としての修行期間がある。だから、仏教はかけ離れた世界だとは思えないのです。
【まさとみ☆】高橋監督は、仏教とどのような関わりをもってらっしゃるのですか?
【高橋】毎日、読経もしますし、精進潔斎みたいなことをする期間もあるし、いわゆる禅定といいますか、坐禅みたいなことをする時もあります。修行の途中です。まだまだ駄目ですが(笑)。【まさとみ☆】心の在り方って、仏教はでは重要なものなんですよね。今の時代、仏教の心を忘れている人が多いのが現状です。 今回、映画『禅』からは、本当に人間の在り方や考え方が伝わってきました。
【高橋】近代合理主義の弊害というか、自由と個人主義が一番気になるのです。我々を含めた、我々よりちょっと上の世代が自由と個人主義を履き違えた。その姿を見た今の若い人は、もっと間違えていく。そういう意味では、きっと我々に責任があると思っています。
今の若い人にとって、「宗教家ってかっこいい」と思ってほしいんだよね。ただ、アピールの仕方を色々探っておられるのでしょう。見つからないでいるのかもしれない。
例えば、ダライ・ラマが来日しました。両国だったか、僕も行ったのですが、ダライ・ラマへ会いに、若い奴がいっぱいいた。あの人の考え方や思想。そういうことに共鳴して、来ている人もいるでしょうけど、どこかで何かかっこいい存在なのです。本当に若い人でいっぱいでしたよ。ある種、僕は可能性があると思った。日本の仏教にも。こうすればいいんだということは見つからないけれど。若い人の宗教離れとか、仏教離れというのは、おかしな教団があって、すごいネガティブなこともありましたが、結局は宗教家であったり、我々の責任だと思います。
【まさとみ☆】ダライ・ラマ氏は逆境においても常に穏やかであるし、存在が際立ってらっしゃいますね。
【高橋】たとえば、曹洞宗を例に出して永平寺の貫首さんが宮崎さんから誰に代わったのか、たぶん若い人は誰も知らないと思いますよ。指導者の顔が見えてこない。
【まさとみ☆】何か、自分に近くない。だから遠い存在になるのですね。
【高橋】顔が見えてこないのは身近じゃない。身近じゃないことは日常じゃない。けれど、道元禅師の存在というのは、今の時代でも日常の中に生かせる心や形だと思うのです。示した道というのも、今の日常にそのまま持ってきても全然矛盾がない。僕流の言葉でいえば、仏教って「ごめんなさい」「ありがとう」「はい」。この3つで、僕は日々にこれを意識することが、仏教修行だと思っています。たとえば「はい」は覚悟であったり、帰依であったり、受け入れだと思うしね。
【まさとみ☆】どうしても「でも」「だって」がついてしまいますね。それをなくして、ありのまま感謝の気持ちを持つことが大切だと思うのですが、なかなか実行に移せませんね(笑)。
【高橋】そうなんですよね。僕が今一番好きな言葉が「放下」です。放下ということができれば、「はい」「ごめんなさい」は自然にできると思うんですよ。
【まさとみ☆】そうですね。自分と向き合うと、自分のことが一番見えてこないですね。
【高橋】自分と向き合うと、余計に自分の我みたいなものが出てくるんだよね。仮にそれが出来たとして、「空」になれますか? それだけでは人間というのはつまらないはずなのです。「空」を超えた何か、「有」ではない「妙有」というのでしょうか。「有」「無」「空」の向こうに「妙有」があると思うんです。
【まさとみ☆】今までとは全く違う「空」を超えたものですか?
【高橋】そこは絶対にチャーミングなはずなのです。そこが何かを示してあげると、人ってもっと仏教なら仏教に向くんじゃないかなと思うんです。これは決してご利益ではない。どうしても何か入り口ってご利益っぽいのが多いじゃないですか。そういうものを全部超えて「有」「無」「空」を超えた何か向こうの「無」というものが、提示できないのかなという気はしますね。提示してほしい気がするし。
【まさとみ☆】監督にとってチャーミングなものって、何か思いつきますか?
【高橋】放下ということが、まずは大理想だよね。ただそれはつかめなくても、そういう理想に向かって行くことって、やっぱり大事じゃないかな。
【まさとみ☆】人間って、生まれてから死ぬまでが本当にゴールではないですものね。
【高橋】死んでからだって、ゴールはないと思うんです。僕は、死んでからのほうが長いと思っているから。
【まさとみ☆】輪廻転生ですか?
【高橋】輪廻なんかしたくない(笑)。しなくて済むようになりたいと思っています。もし、極楽というものがあるとすれば、ずっと極楽にいたいじゃないですか。
【まさとみ☆】いたいです!
【高橋】地獄で何万年生きるかと思うと、ぞっとするよね。だからこそ、どうやって死ぬかが大事ですよね。人生というのは、延々と続くであろう境涯をたぶん決めるんじゃないかな。
【まさとみ☆】高橋監督にとってどんな死に方が理想ですか?
【高橋】一番小さなことを言えば、「ああ、そこそこいい人生だったな」と思いたい。ただ、あと何年生きるかわかりませんが、懺悔し尽くせたらいいなと。
【まさとみ☆】懺悔し尽くすとは?
【高橋】数が多すぎて懺悔しきれないんですよ。「ごめんなさい」をしながら、また新たに「ごめんなさい」をしなければならないことを、自分で生み出しているわけでしょう?
【まさとみ☆】確かに、歩く後ろからついてくるみたいなものですね。
【高橋】過ちに気付いたら、それを繰り返さないはずなんです。それが「またやっちゃった」になるんですよね。
【まさとみ☆】人間って、どうしても失敗に懲りない性分ですね。映画の中でも、おりんさんへの性欲にかられ、僧侶をやめてしまう俊了もいましたが。
【高橋】ああいうのは、俺です(笑)。おりん、松蔵とお坊さんの俊了。これは俺を三等分ぐらいにしているのかな。
【まさとみ☆】人間らしい部分、ですね。
【高橋】というかね(笑)。自分のだめな部分三等分くらいにして、キャラクターの上に乗せています。
【まさとみ☆】すごいリアルでした。でも、道元禅師って欲求というものにフタをして、厳しい修行をするというのは、普通の人はできませんし、カリスマ性を強く感じました。
【高橋】そうですね。とても足元に及ばない。それでいいと思うんです。大理想に向かって近づこうとするとか、道元さんの足元まで、なんとか届こうとする努力。向かっていくことが大事だと思います。道元さんの表現でいえば、包容力や受け入れということも、この映画に入れたかったのです。最後のシーンで坐禅をする子供の手の中に道元さんを入れたのですが、あれは受け入れてくれる道元さんを表現したかった。
映画でのエピソード
【まさとみ☆】撮影で何か苦労なさった点はございますか?
【高橋】大変だったのは最初の本づくりだけで、苦労はしていませんね。
【まさとみ☆】毎日楽しんで撮影なさったのですね。
【高橋】楽しさの種類はちょっと違います。山登りのような、肉体的なしんどさはあります。それはどんな映画でもあるんです。(中村)勘太郎には、心と形というのをきちっと表現して欲しかった。形なき心は形に現れる。けれども、彼にはその苦労は全然いらなかった。精神的に楽でした。
【まさとみ☆】この映画で一番伝えたかったことは?
【高橋】心と形かな。でも、本来は道元さんがつけた道を歩むためのもの。いきなり普通の人に「この道を歩め」なんていっても無理だと思うんです。だから、道元さんの心と形を、ほんのちょっとでもいいから心掛けて、そこに一歩を踏み出していってもらえばいいんじゃないかな。
高橋監督と仏教の出会い
【まさとみ☆】高橋監督が仏門へ入ろうと思ったきっかけは何ですか?
【高橋】高校時代、親父が突然亡くなったことを契機に、いろんなところへ行ったんです。死んだらどうなるのかと思って。まず、親父の墓を作った寺で開催されていた仏教青年会へ参加しました。けれども、なかなか死んだらどうなるのか教えてくれない。それから、禅寺へ坐禅に行ったり、高野山にこもったり、キリスト教のミサへ行ってみたり、いろんな本を読んでみたり。その時の体験で、道元禅師のことは頭の中に残っていましたね。
その後、東京へ出てきてから無茶苦茶な生活をしました。多すぎて懺悔きれないくらい。その当時、仲間のひとりと1年半くらい会わない時期があり、偶然再会したら、激変していたんです。「どうしたんだ?」と聞くと「実はちょっと仏教を始めて」って。話を聞いているうちに、自分も仏教をやってみようかなという気になっちゃった。それがきっかけです。
【まさとみ☆】友達はどのように変貌されていたのですか?
【高橋】もともと小さなバーでママをやっていた女性で、自分の店を開く前に、別の店で酒を飲んで、終わってから朝までまた飲む。それこそ結婚しているのに、男をとっかえひっかえみたいな女性だった。それが、一年半くらいぶりに酒場で偶然再会した彼女は、お酒ではなくお茶を飲んでいるんです。顔と口調がまったく違うのね。
【まさとみ☆】監督がおいくつの時ですか?
【高橋】32から33歳の間です。だから、仏教を始めたのは33歳だと思います。
【まさとみ☆】その女性は高橋監督の人生を変えた方ですね。人の生き方を変えるほど、やっぱり人って影響を持つのですね。実は私も、高校・大学時代に姉と母を亡くしました。それから、生きること、死ぬこと、あの世の世界などは身近な存在に感じています。人間の生き方は、人の生死や生きる方向性にすごく影響を与えるのだと実感しますね。
【高橋】それは当然、日常とかかわるものだし、人生とかかわもののはずですよ。だからこそ、当然のことだろうと思います。
【まさとみ☆】高橋監督の生活はどのように変わっていったのですか?
【高橋】まず、人を殴らなくなりました。もう毎日のように喧嘩していたからね。僕は体の中に2つ、刃物傷がありますよ。
【まさとみ☆】一度身につけたものって、脱ぐのはなかなか大変ですよね。
【高橋】ちょうど結婚することが決まっていたのですよ。やっぱりこのままの自分ではだめだろうとう意識はあったと思います。
【まさとみ☆】本当にタイミングが良かったんですね。
【高橋】仏様は知っているんですよ、その時期を。「こいつに会わせよう」と。「どうするかおまえが選べ」みたいなことだと思います。
【まさとみ☆】高橋監督の生き方を180度かえてしまうほどの世界観のある仏教。最後に、仏教離れをしている若者に何かメッセージを頂けますか?
【高橋】仏教と向き合うと人が好きになる。他人が好きになる。それで充分じゃないですか。
【まさとみ☆】そうですね。他人も嫌いだけど、自分も嫌いだという人が多いですもの。他人が好きになって、またそれで自分も好きになる。そのきっかけが仏教である。今日はどうもありがとうございました。映画の成功を祈っております。
(撮影・小倉隆人)
 歌舞伎俳優
歌舞伎俳優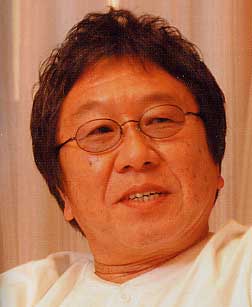 映画監督
映画監督